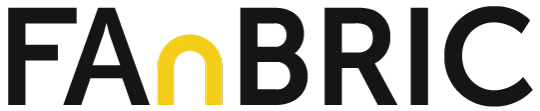産地から探す
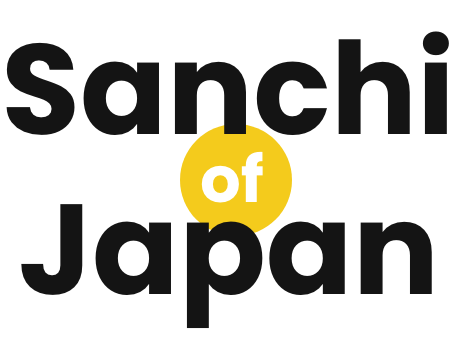
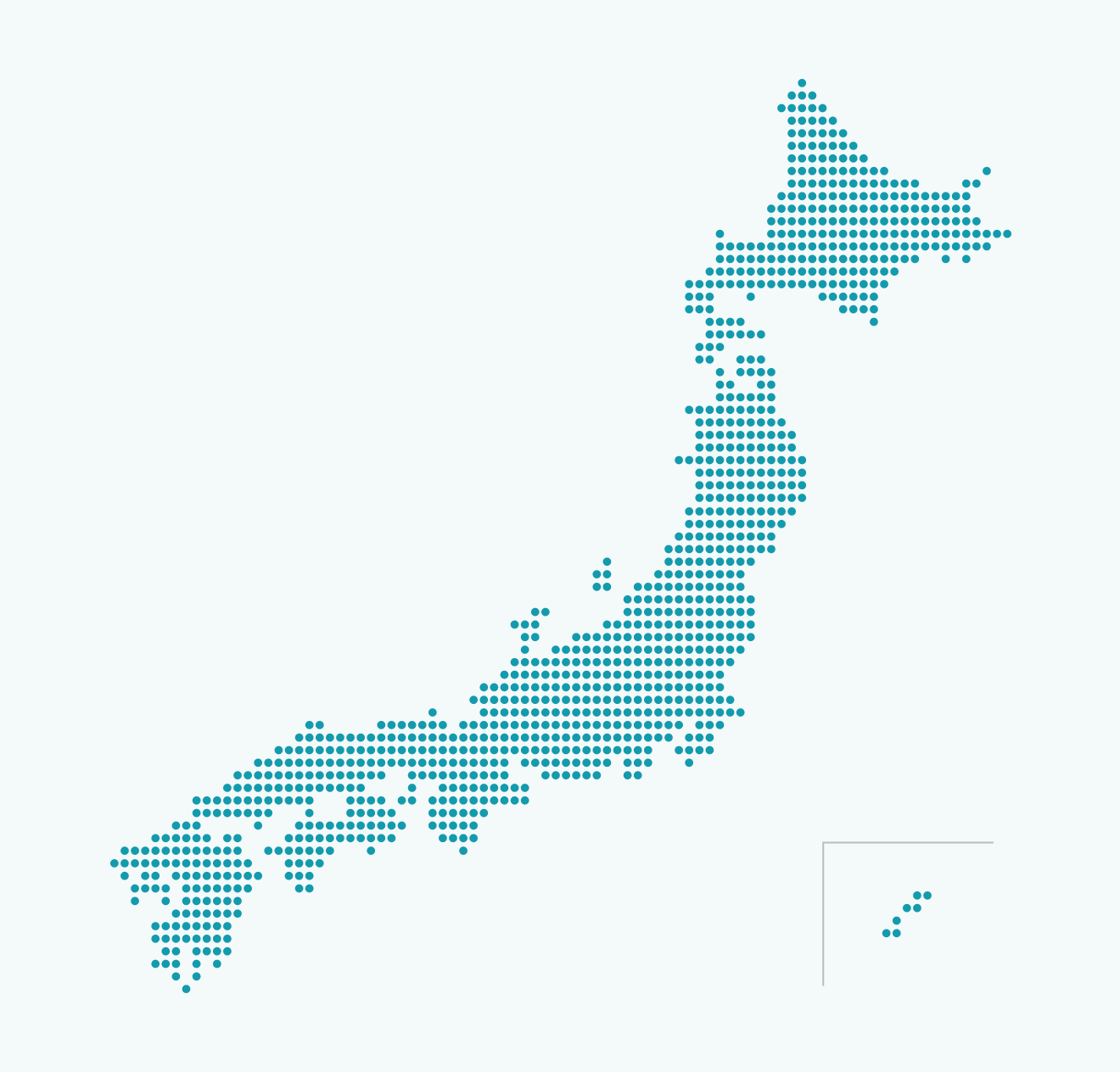
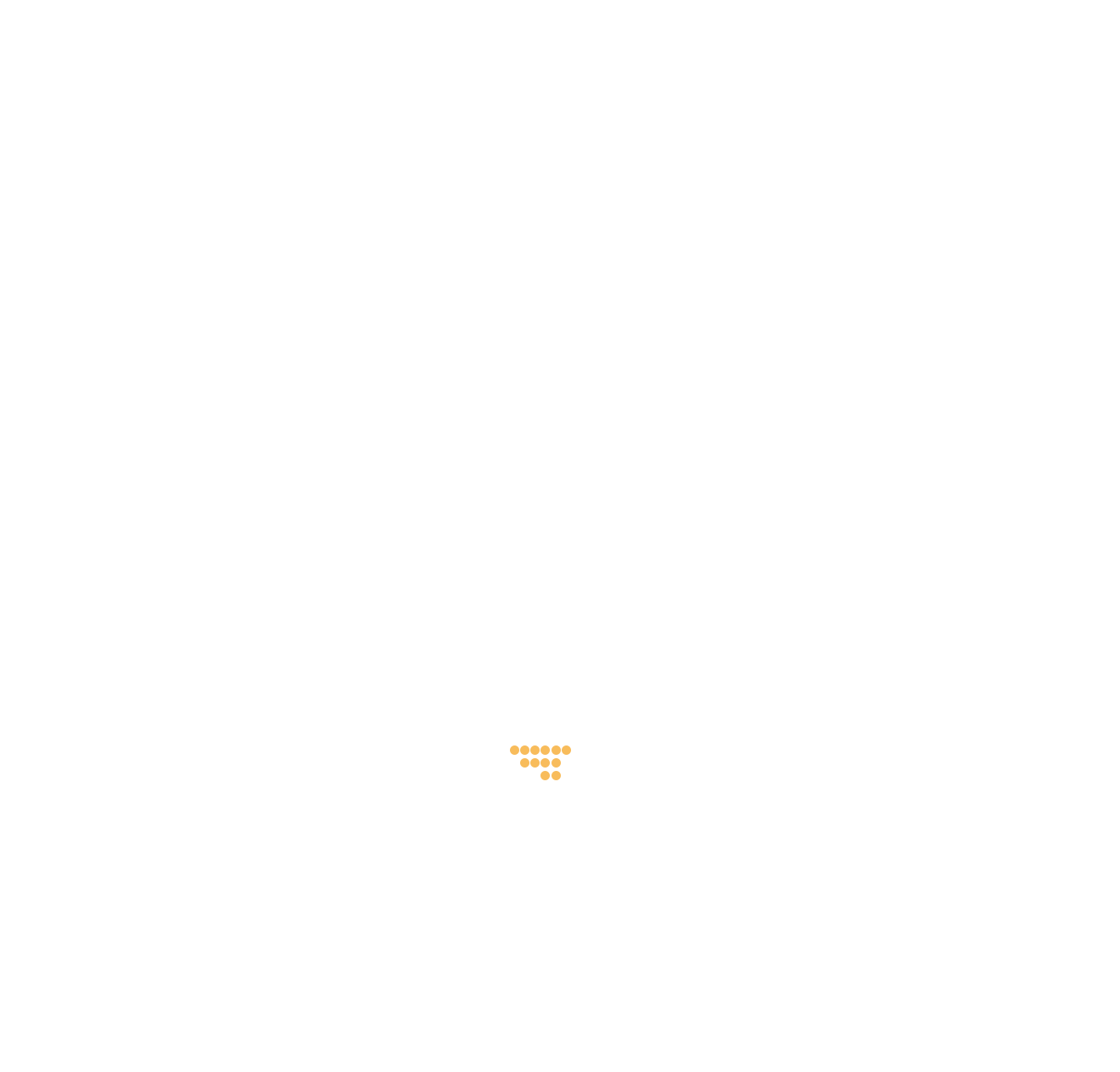
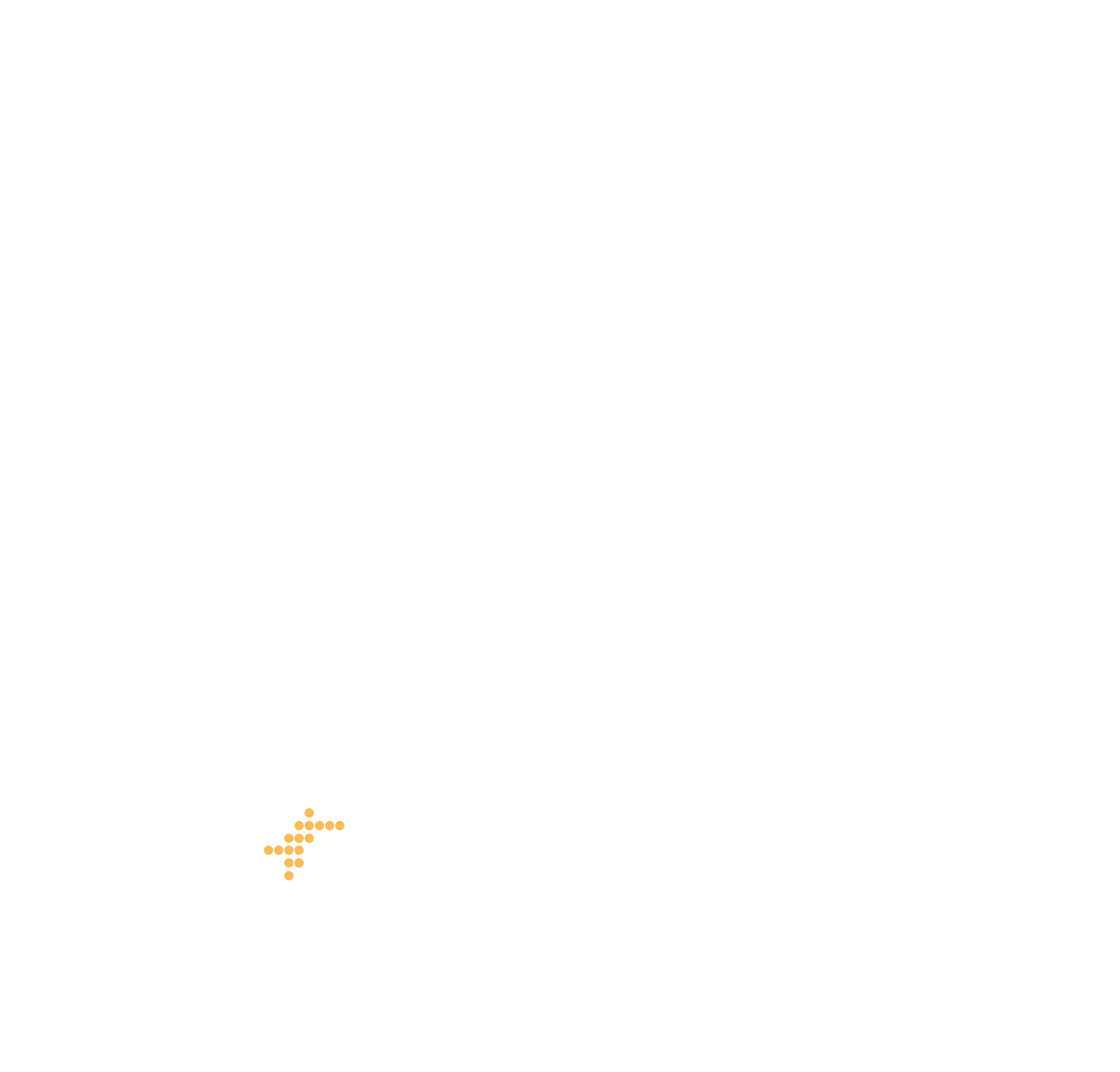
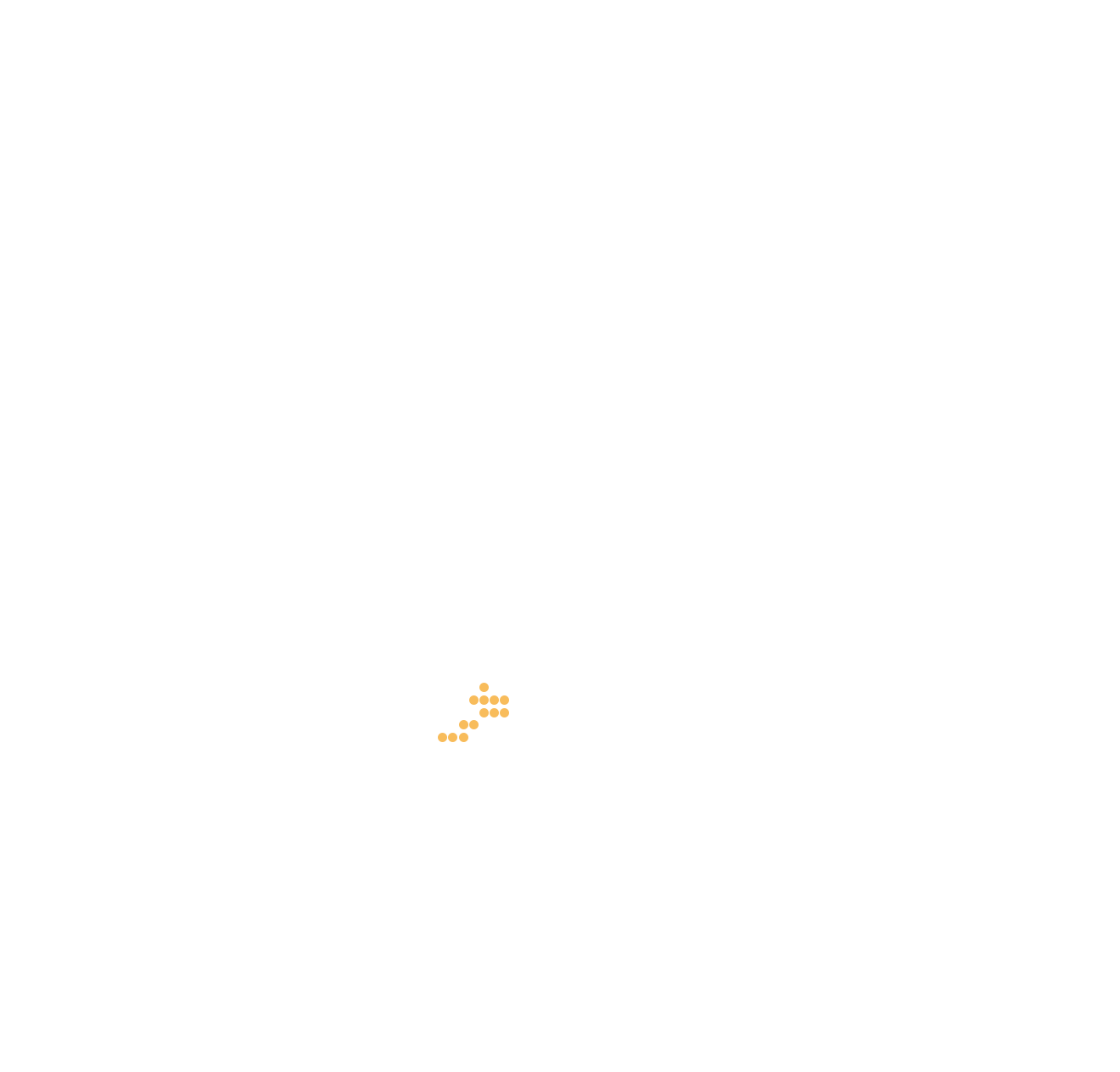
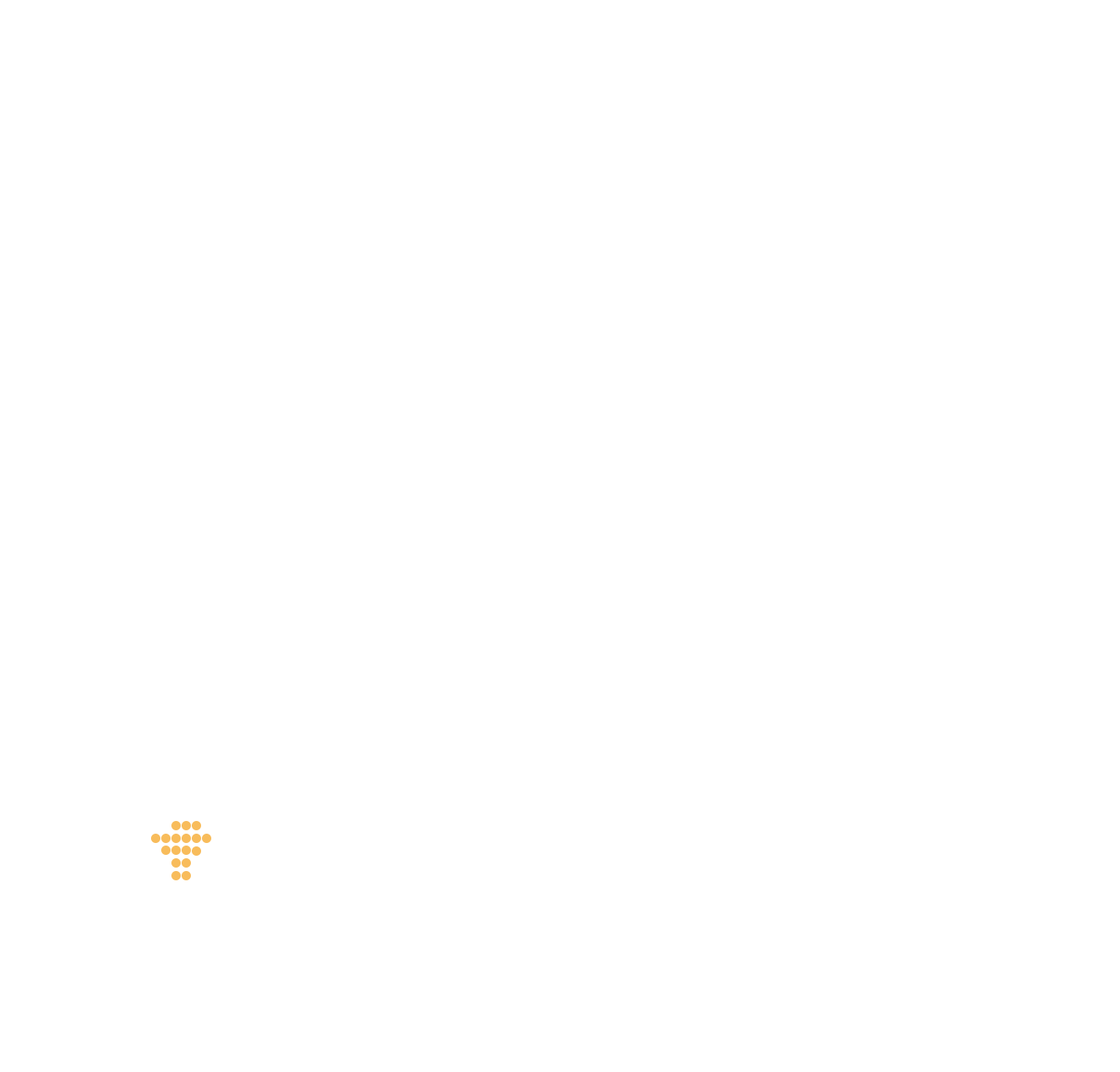
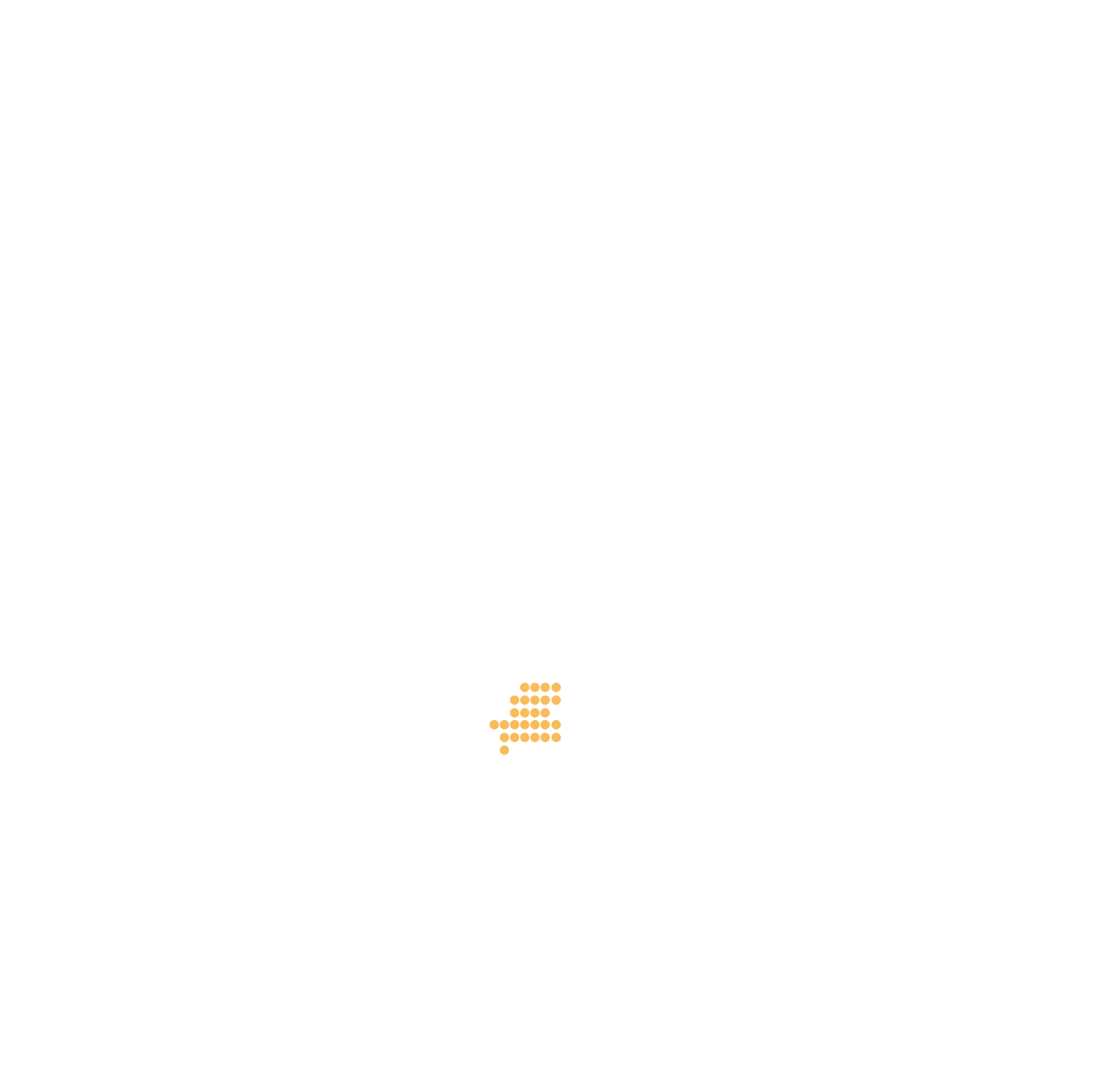
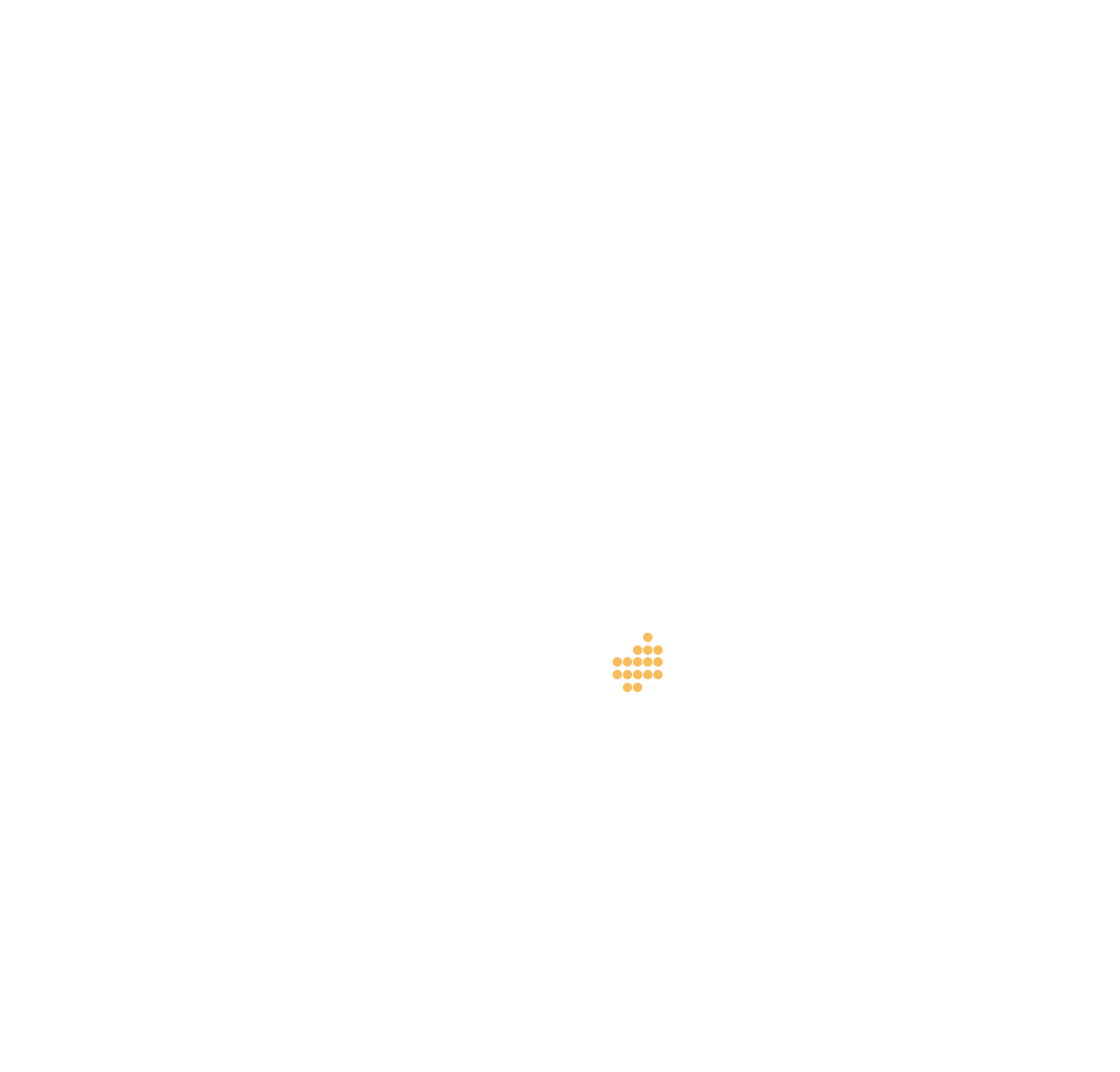
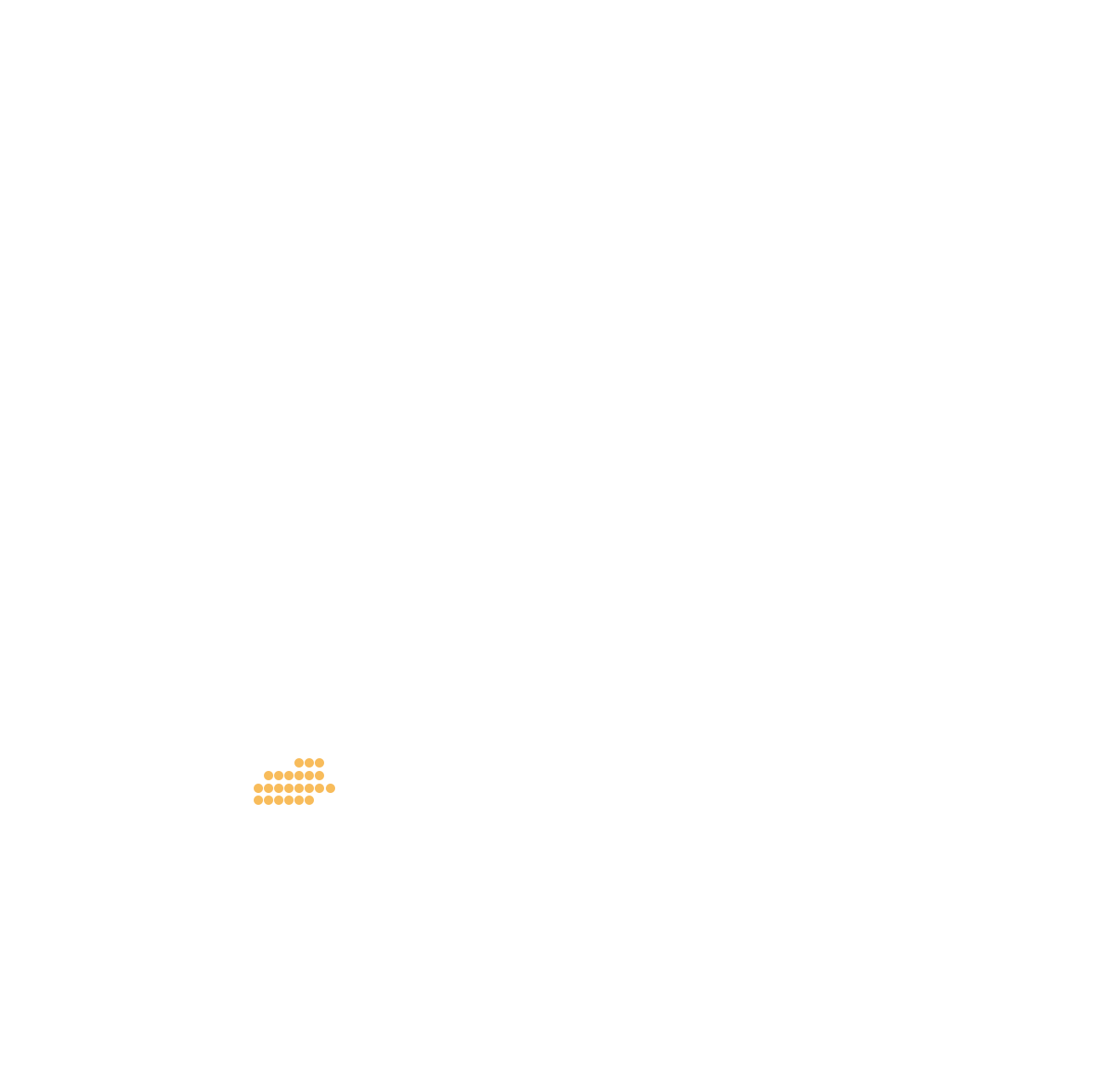
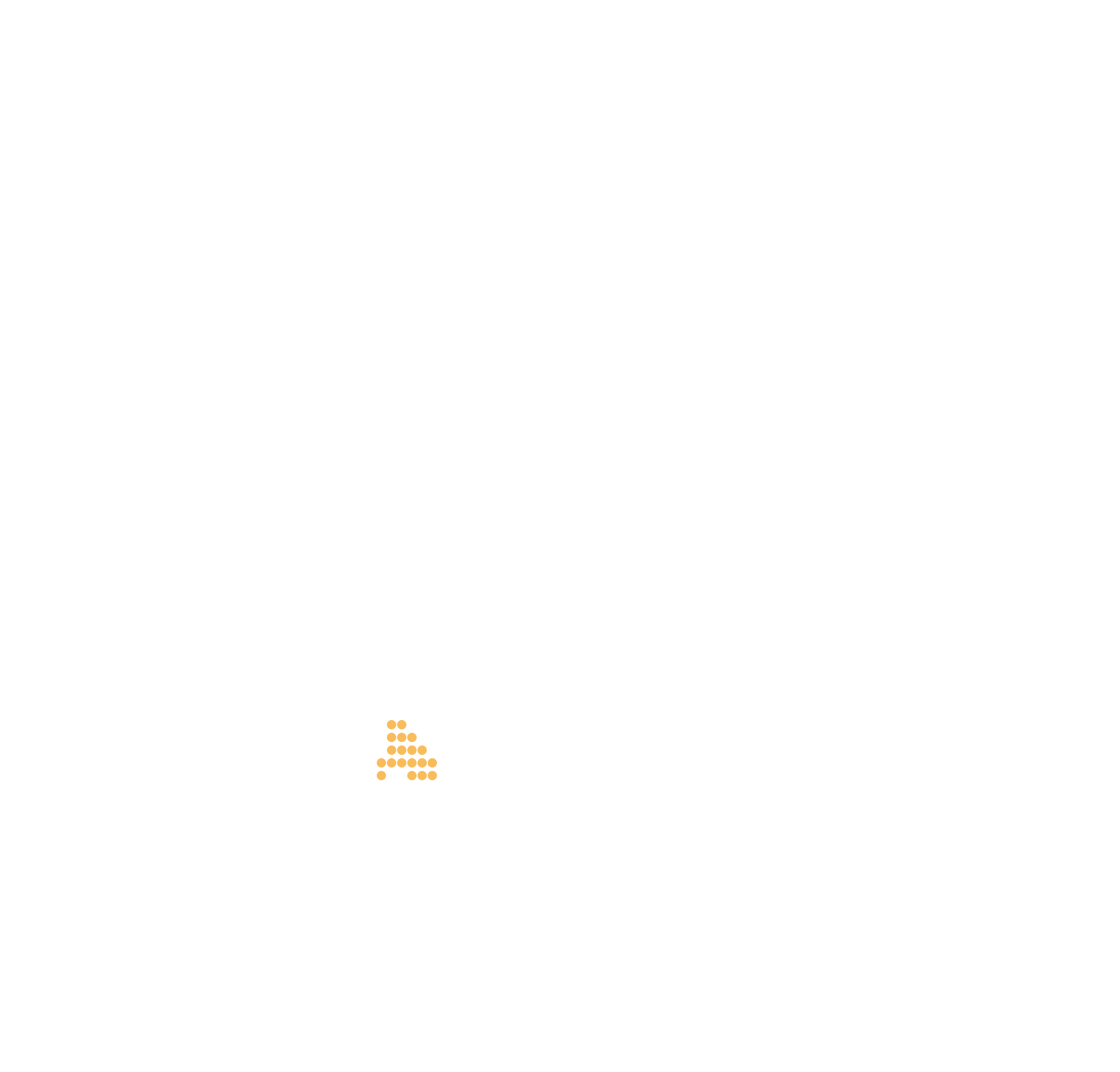
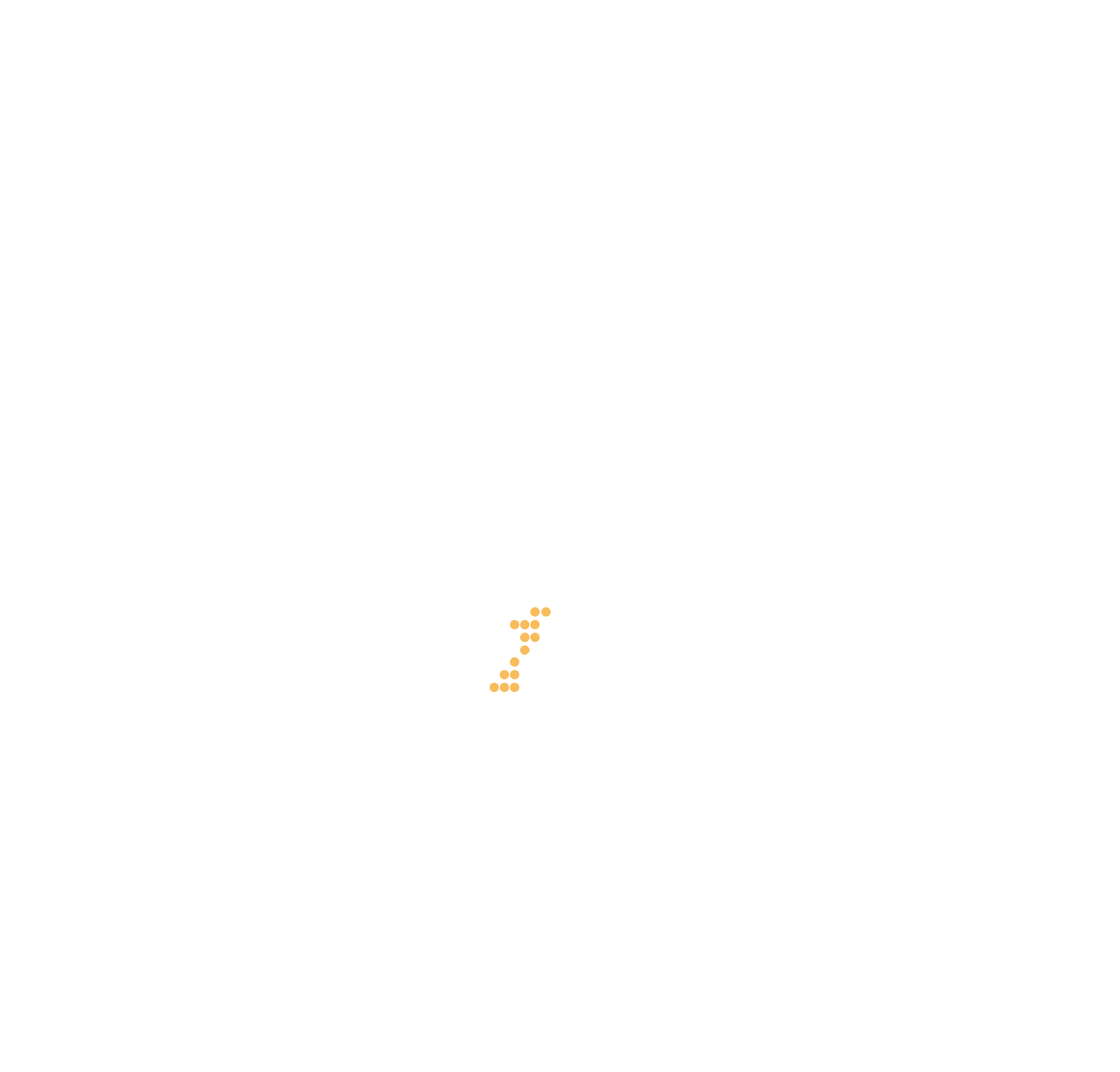
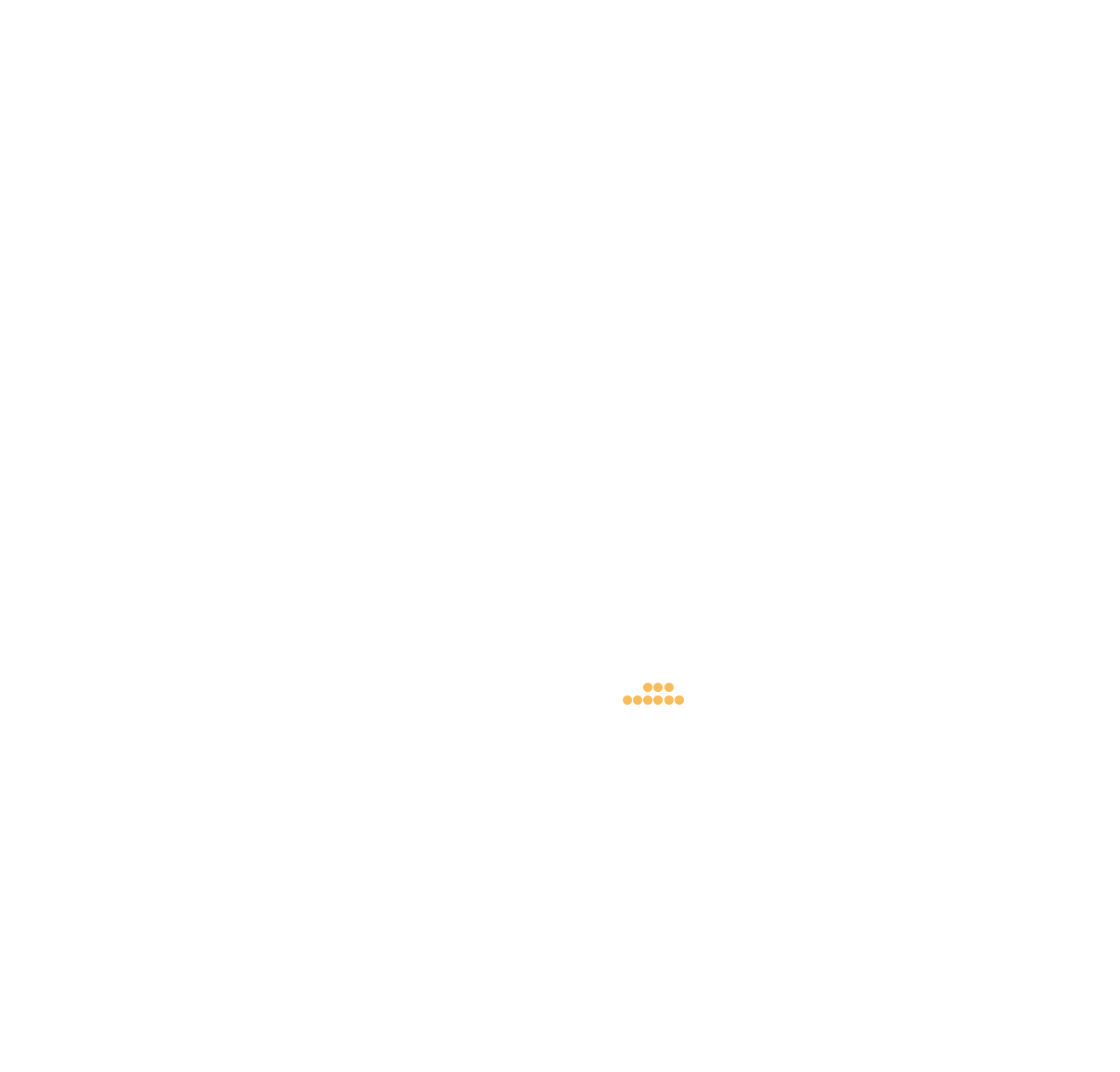
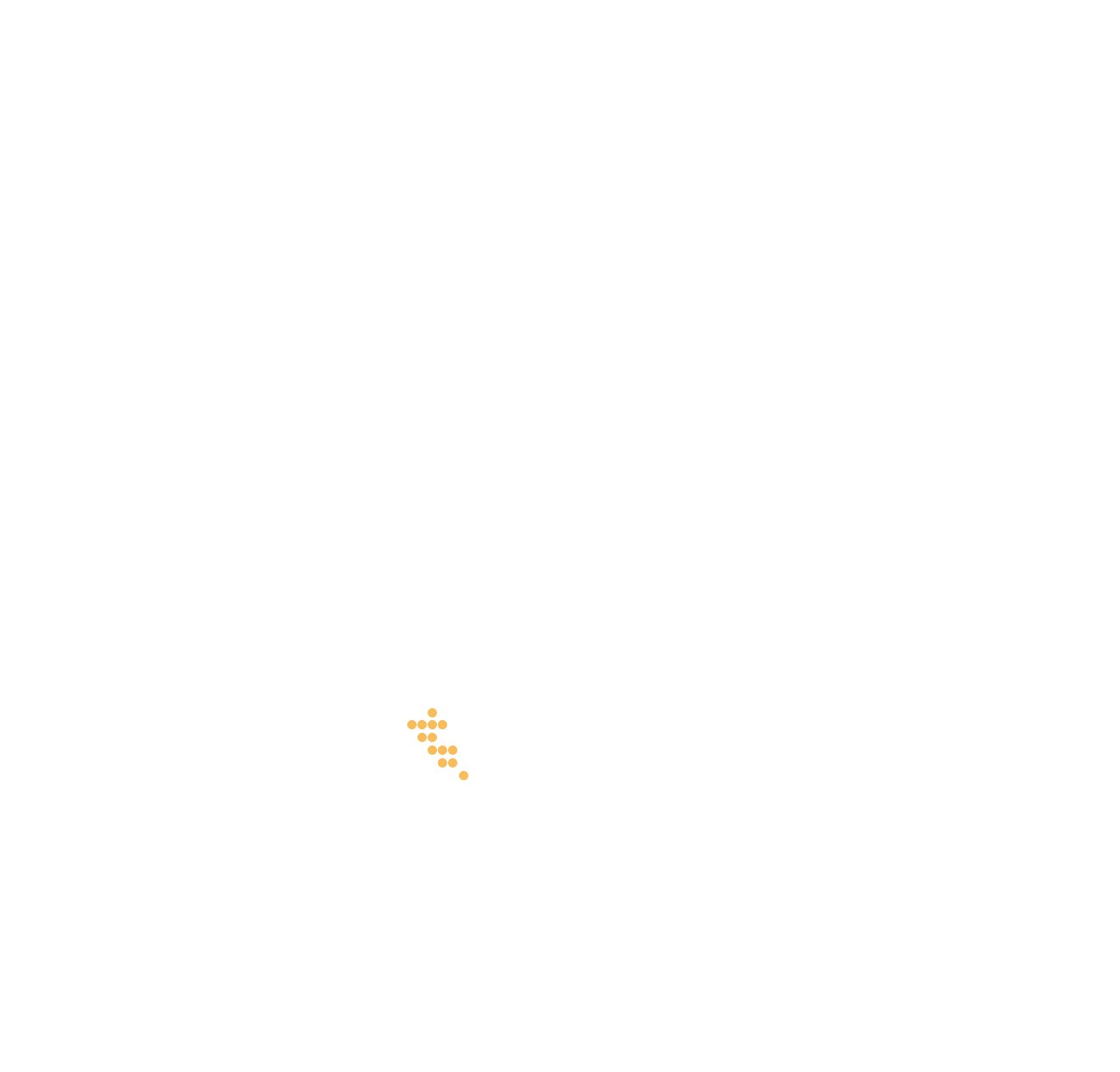
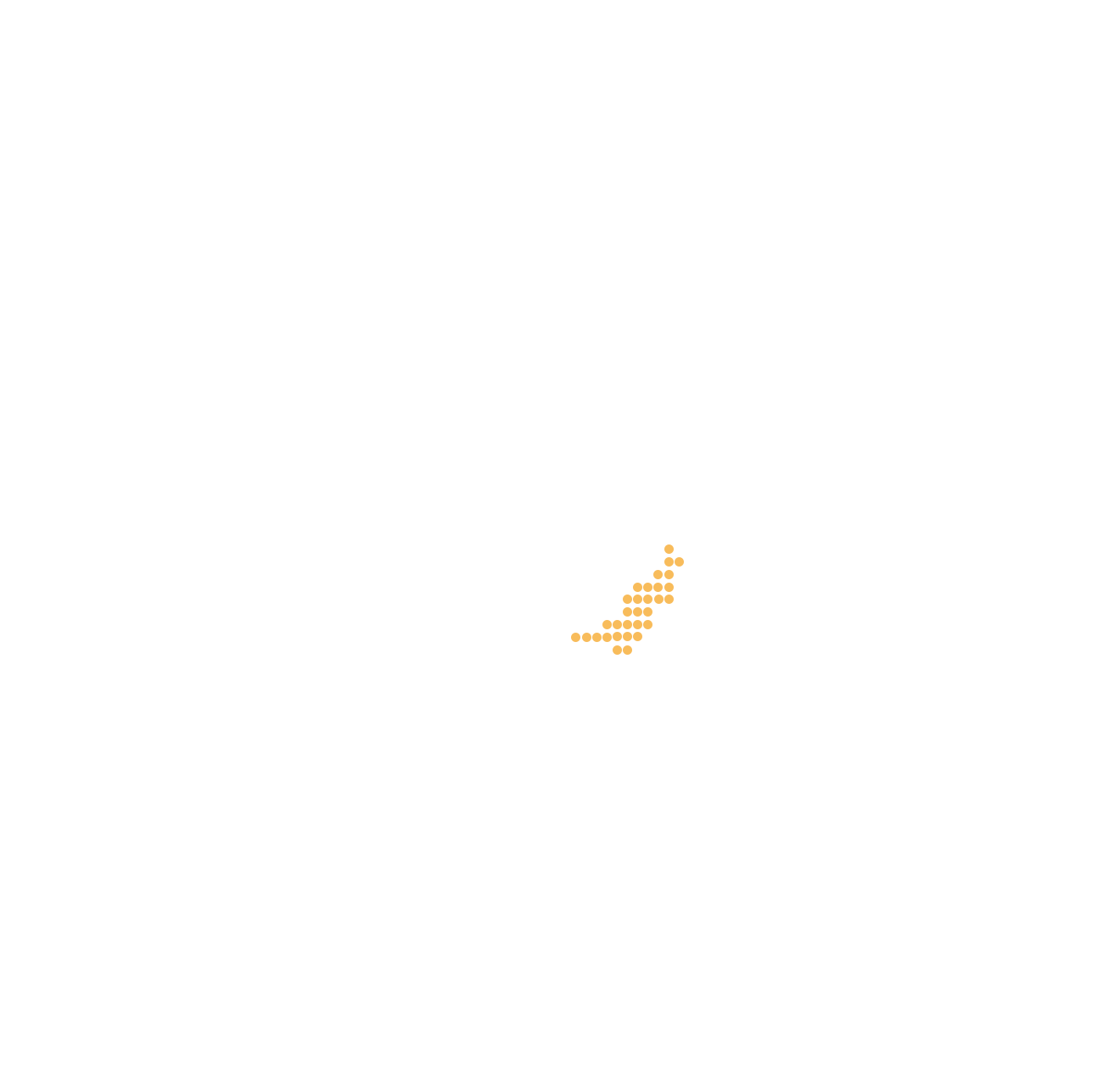
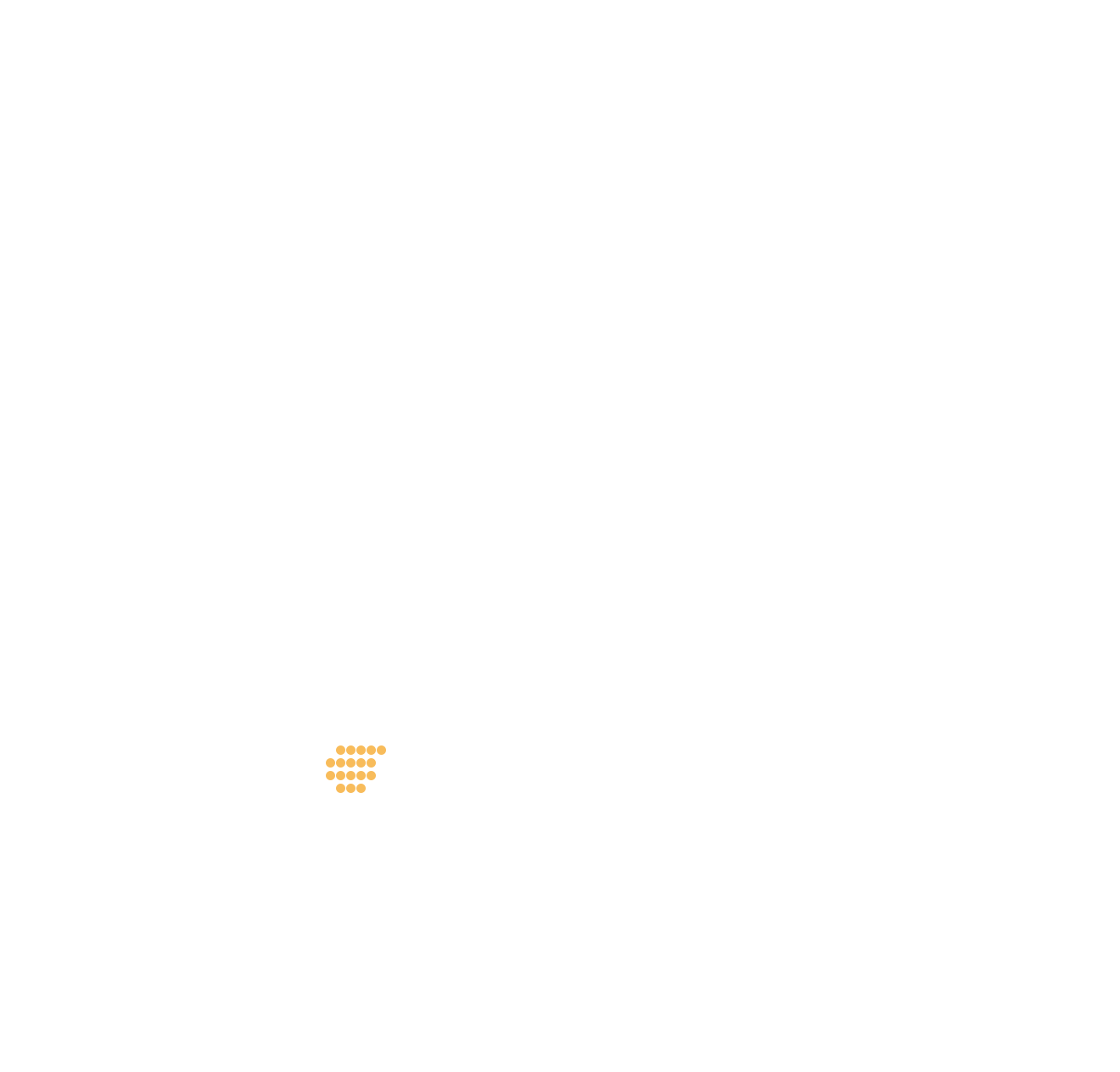
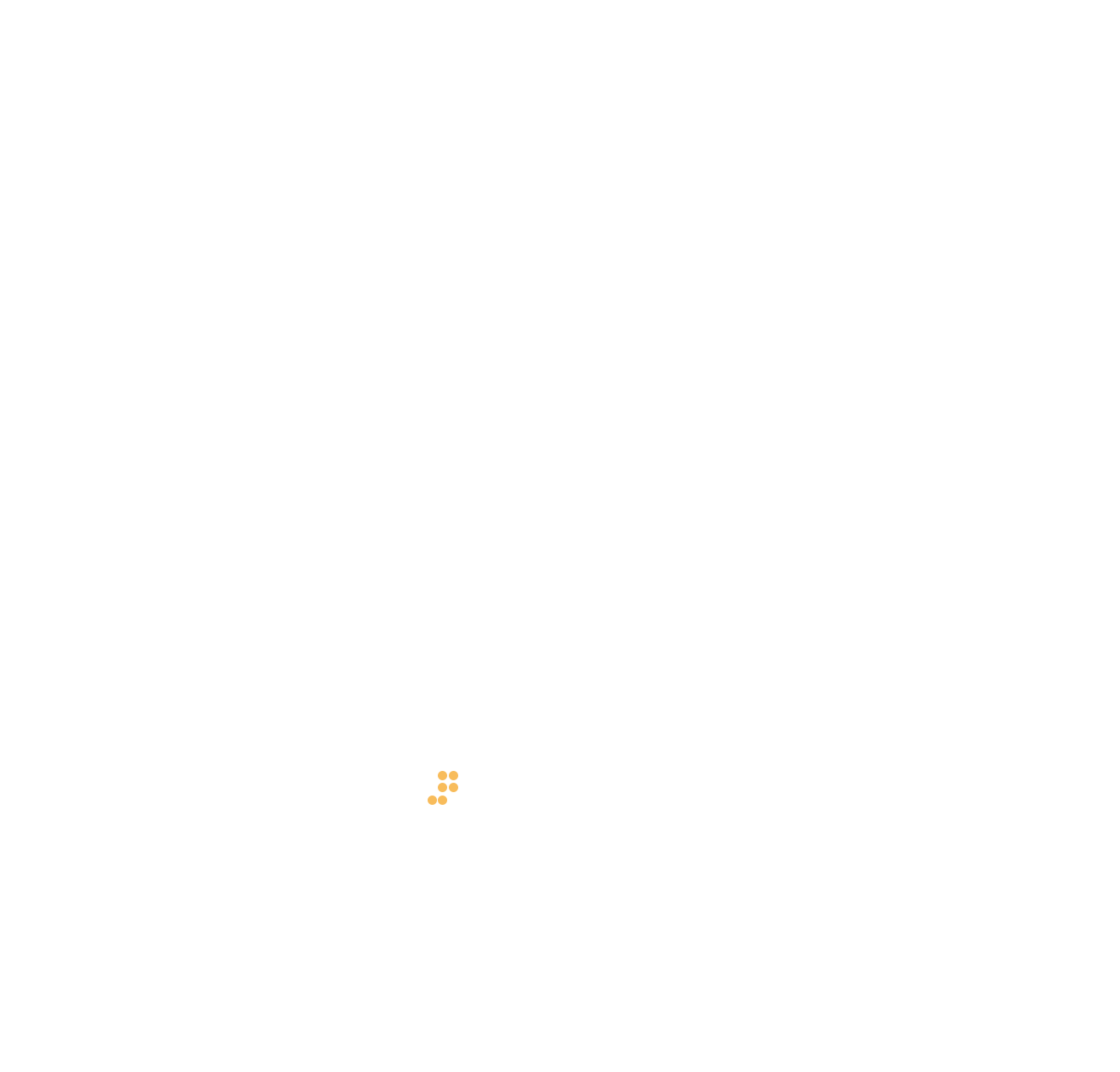
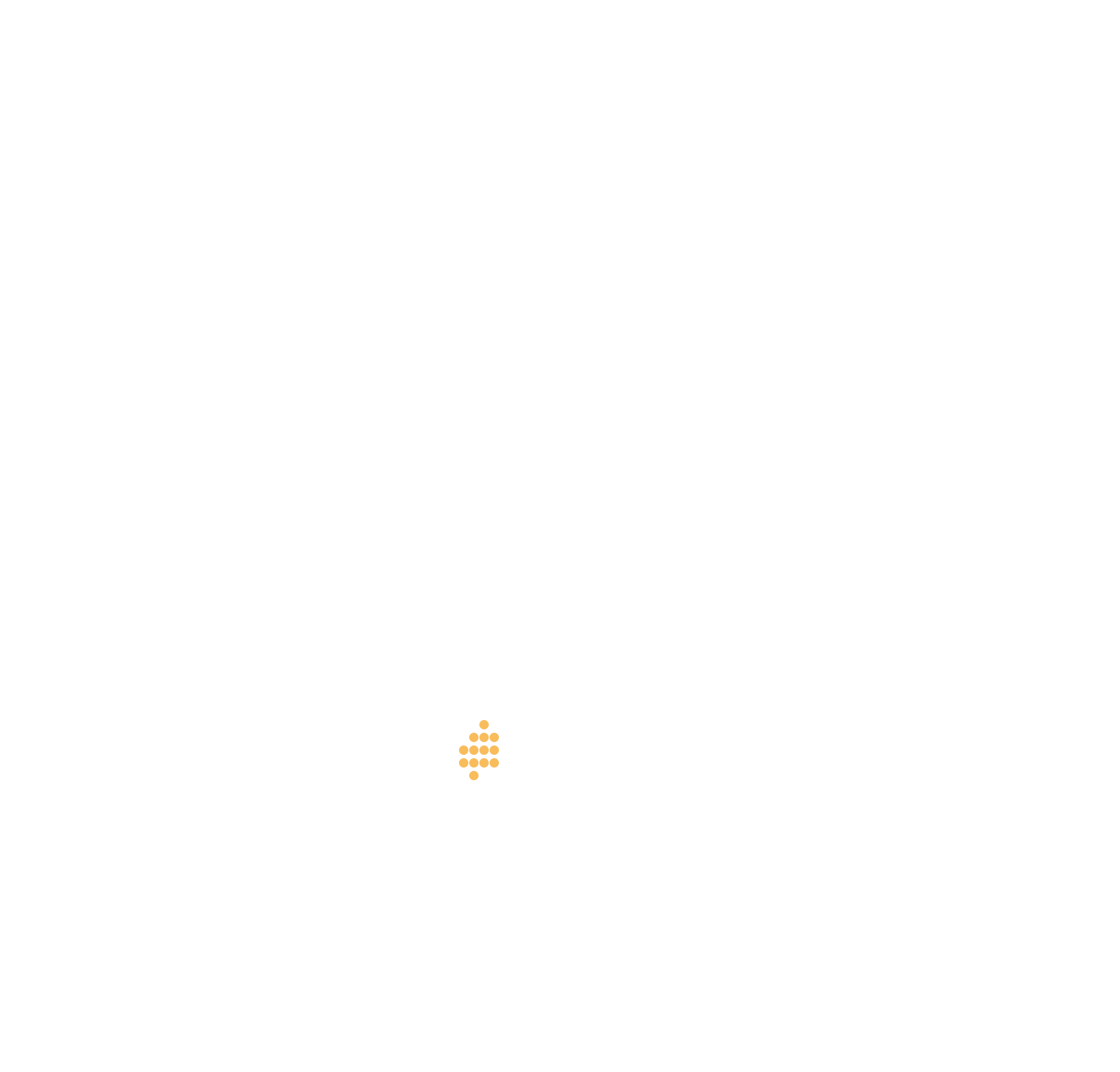
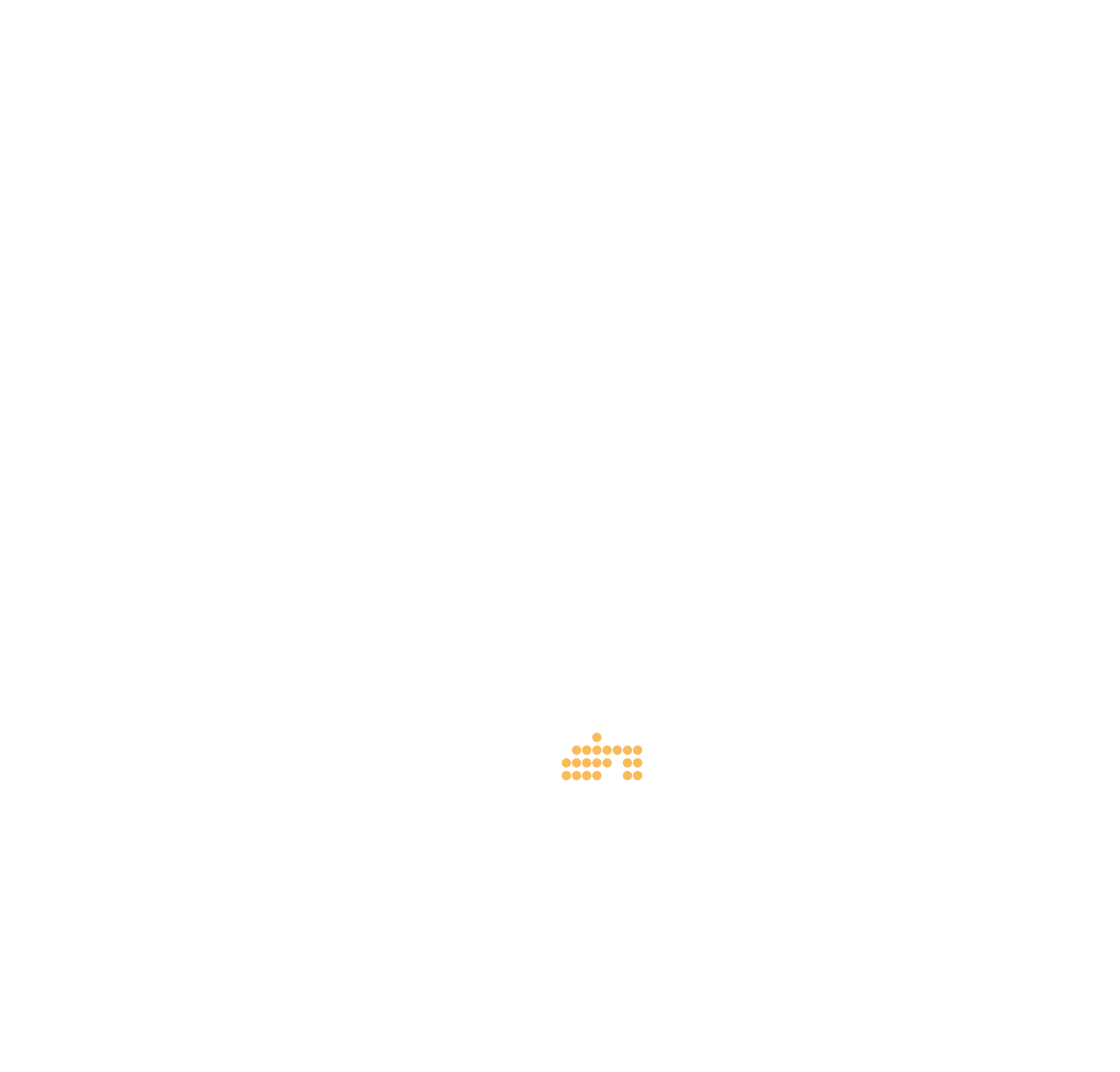
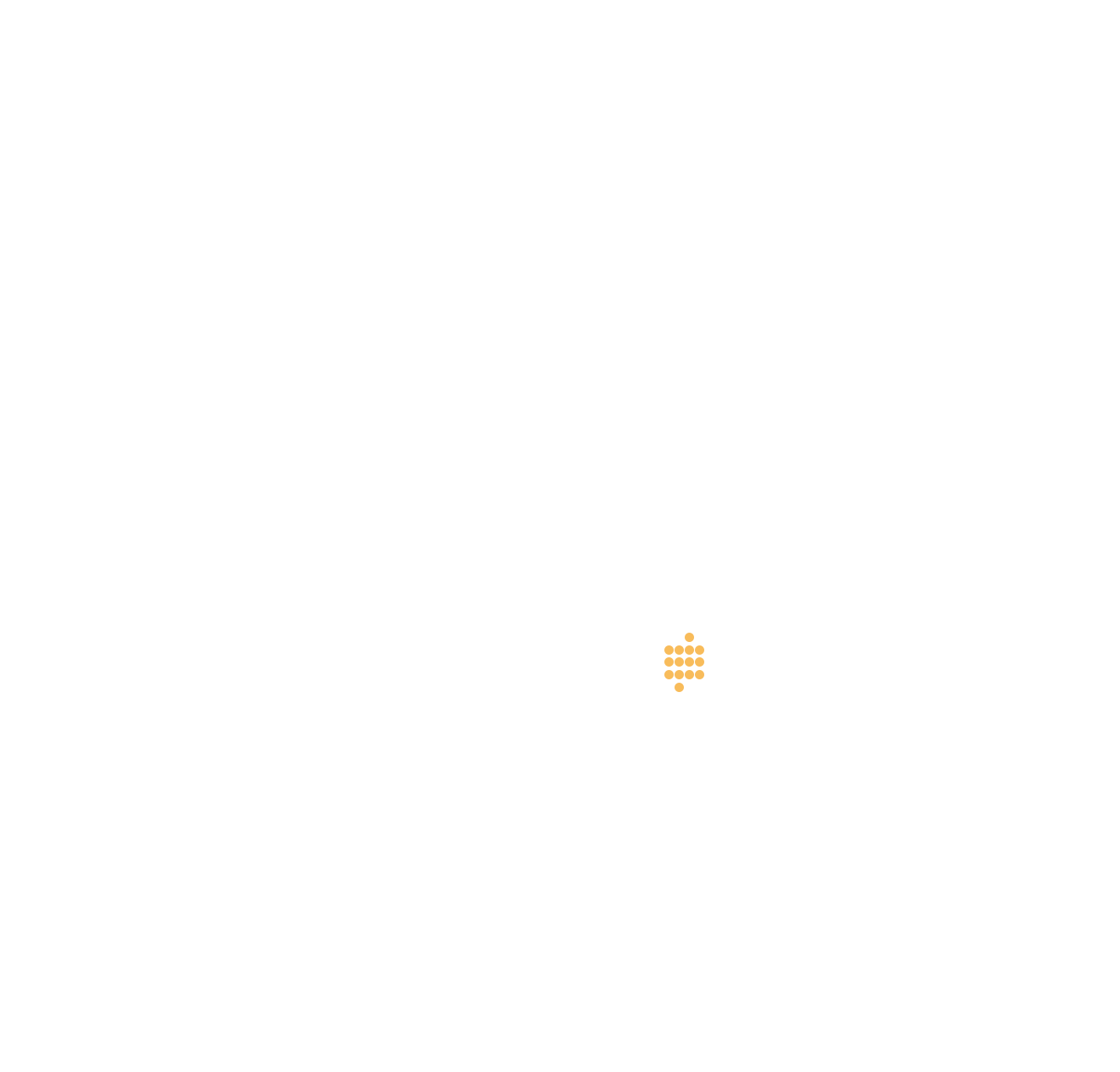
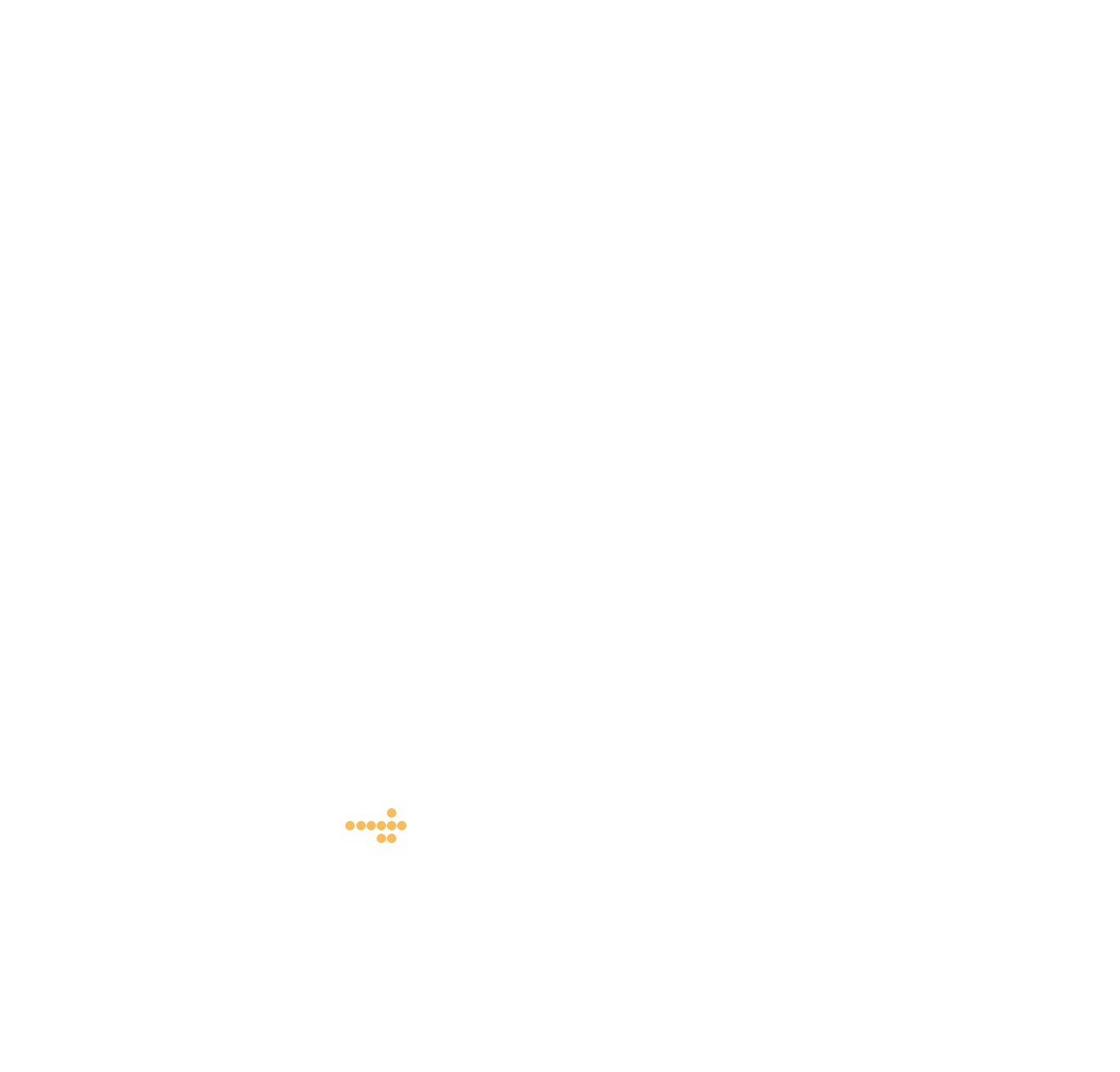
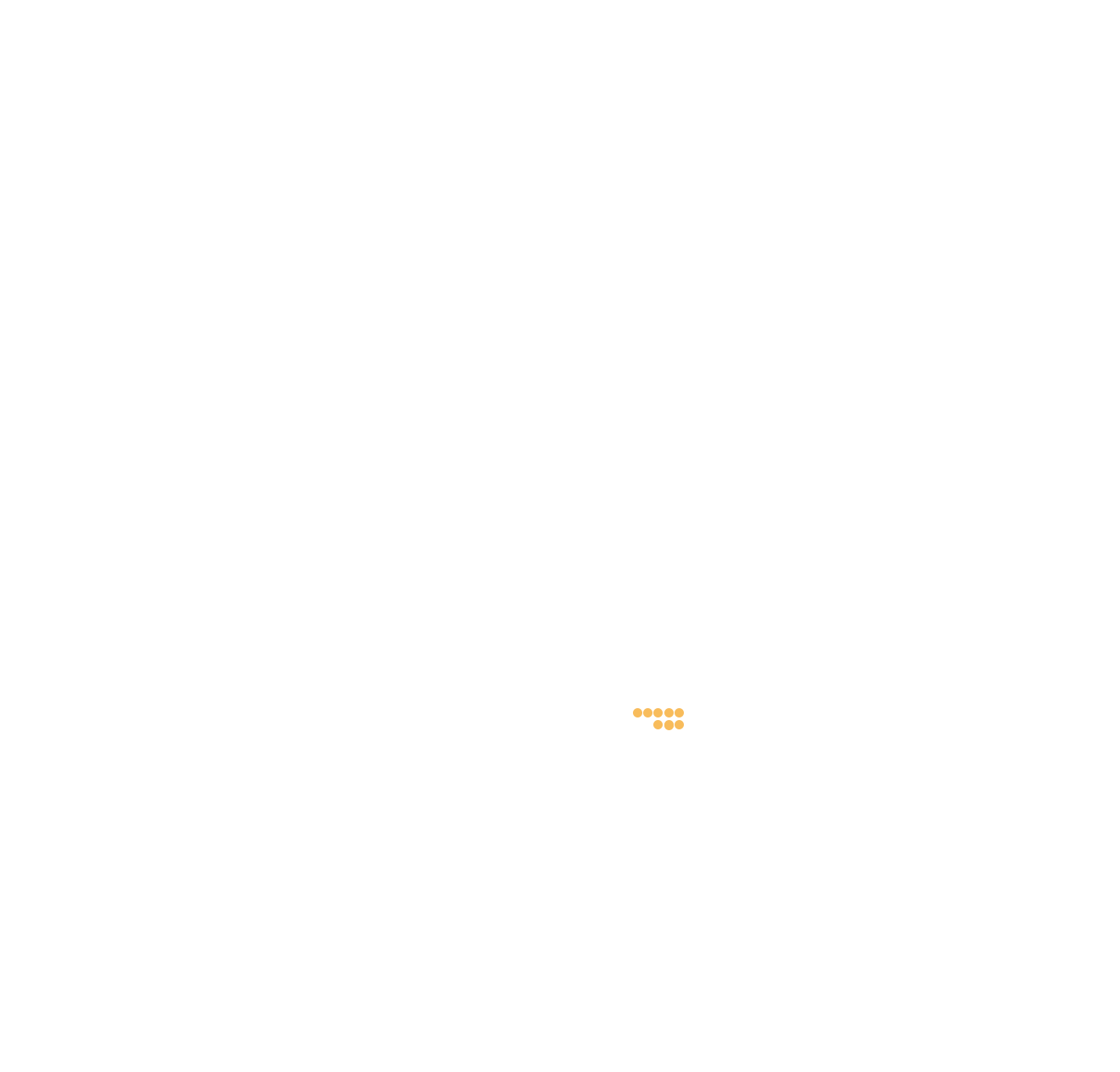
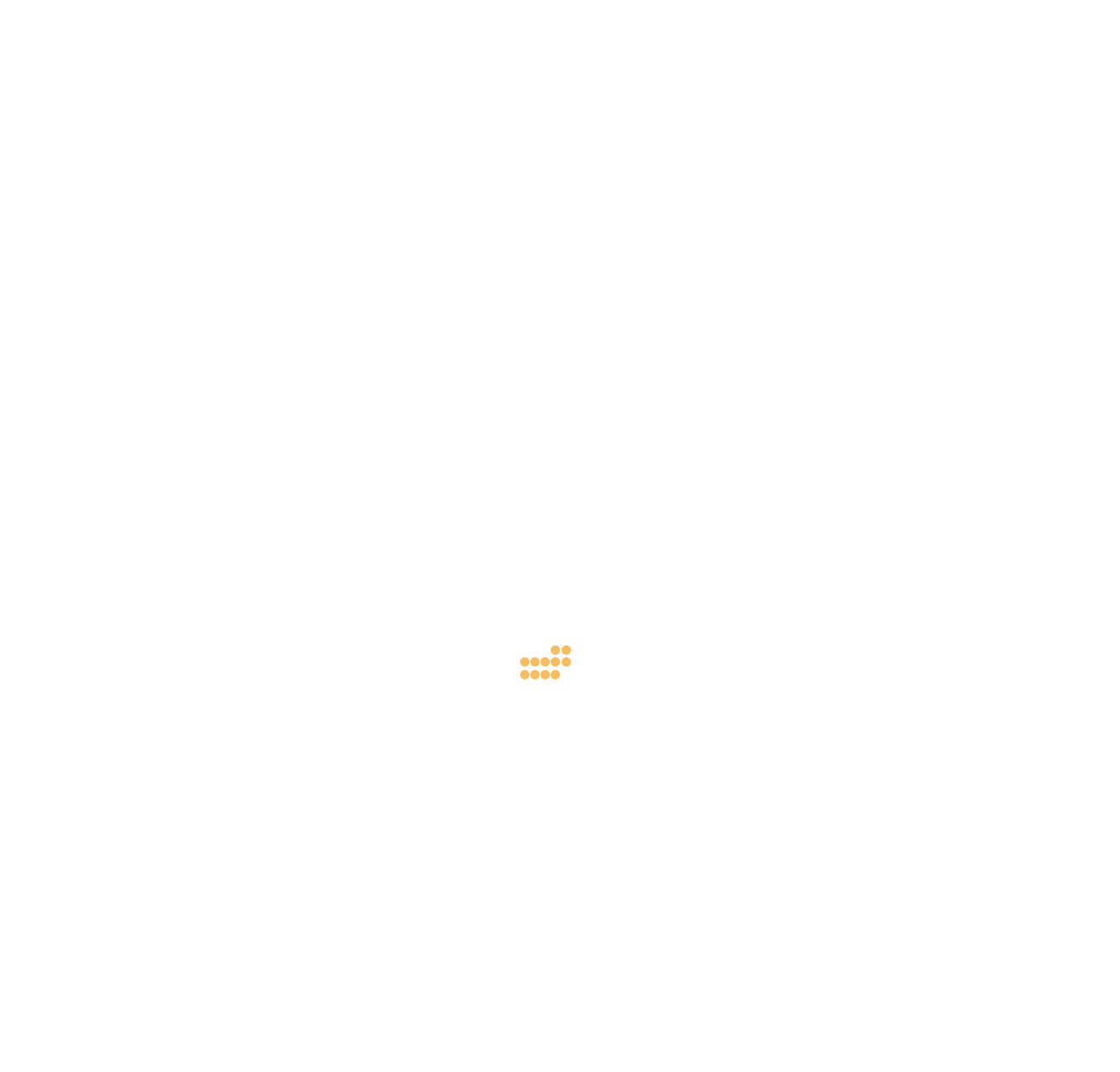
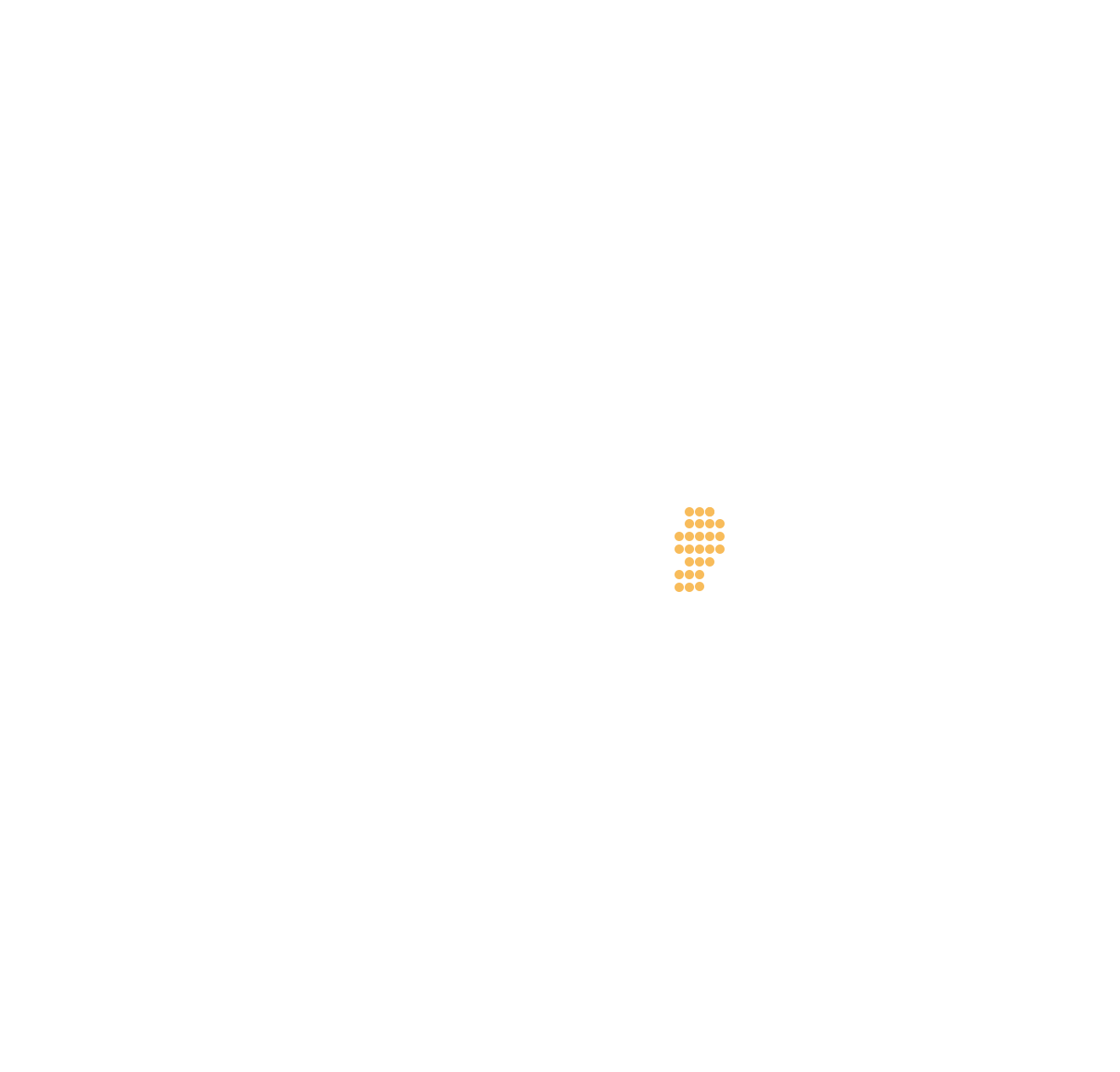
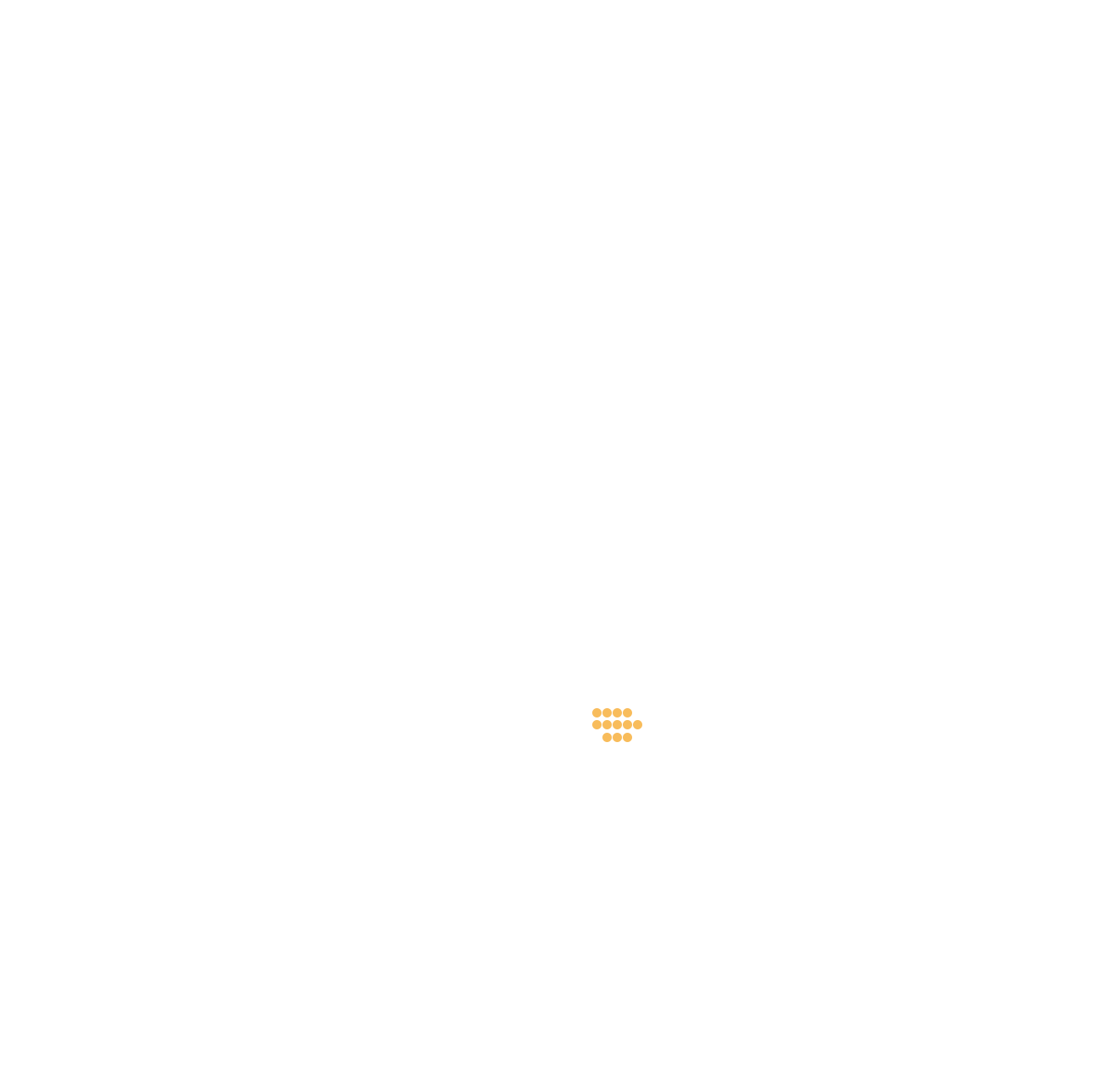
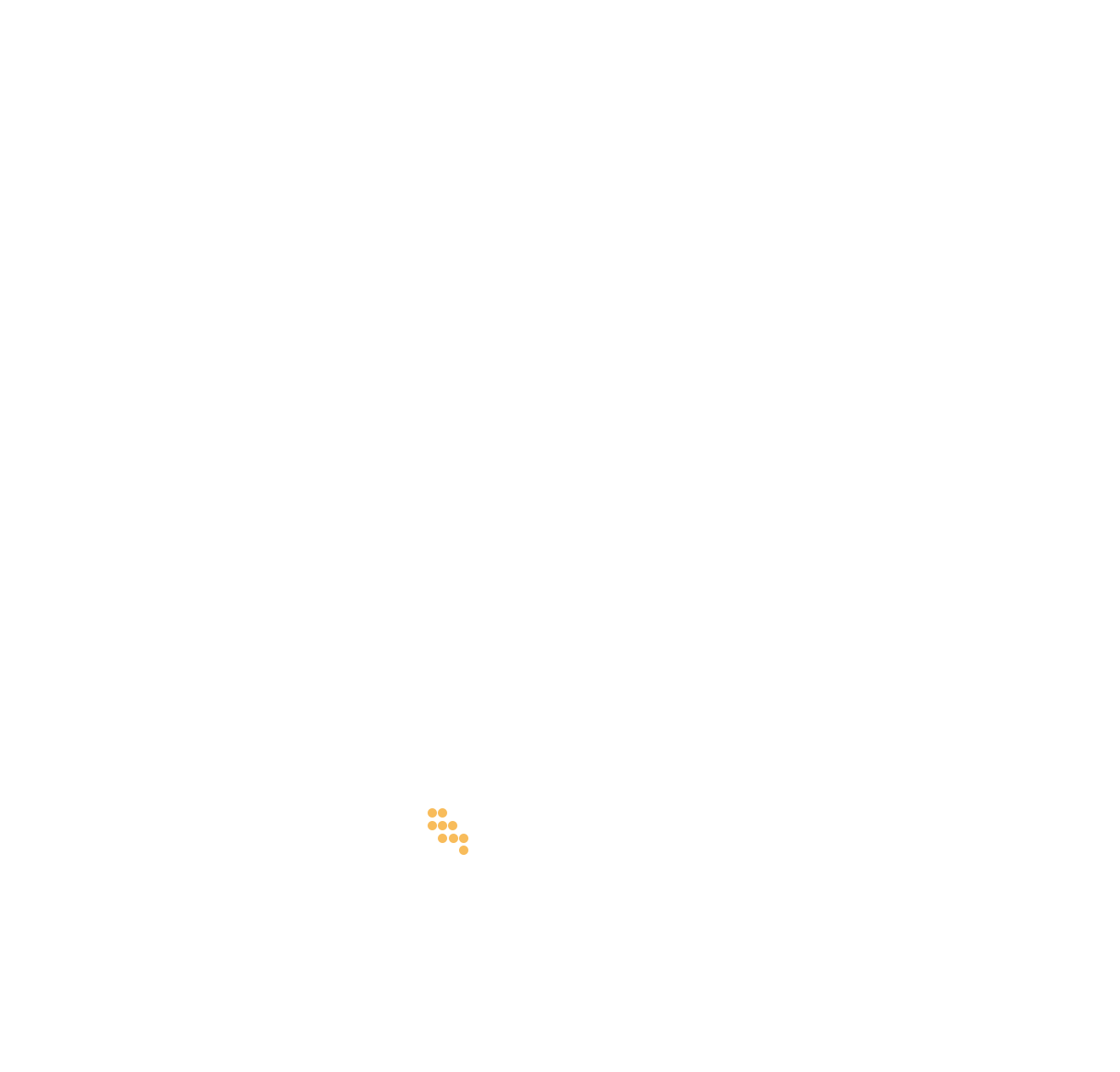
米沢産地
山形県
日本国内で最北に位置する繊維産地。自然の草木で染めた糸で織り上げられる「米沢織」が有名。
当初は麻織物であったが、養蚕が盛んになるにつれ、より高級な絹織物が生産の中心となり発展を遂げ、現在に続いている。
また、明治から昭和にかけて化学繊維の開発にも取り組み、米沢は天然繊維と化学繊維の総合産地として広く知られている。
商品を見る
足利・
佐野産地
栃木県
江戸時代に綿の織物で栄え、明治では絹織の生産に注力し輸出を拡大。昭和初期からは「足利銘仙」で一世を風靡する。
戦後洋装の時代を迎えてからはトリコット(たて編)を中心とした編地の産地となった。また、佐野市は染色から刺繍、縫製工場が集約しており、足利・佐野・群馬の桐生など、一帯を総称して両毛産地とも呼ばれる。
商品を見る
桐生産地
群馬県
桐生産地は群馬県の東部、栃木県との県境に位置する。高級絹織物の生産で栄え、「西の西陣、東の桐生」と称される。
現在は絹織物だけでなく、複合ジャカード織物を中心に、化合繊に関するニット・縫製・刺繍・染色整理業などの多様な生産場が点在している。
商品を見る
飯能産地
埼玉県
1300年以上前に大陸から伝わってきた技術がルーツといわれる飯能・所沢地域は、絹織物の産地として栄え、特に江戸時代から大きく発展してきた。
現在は工場の数は減少しているものの独自の発展により技術の幅を広げており、高品質なモノづくりが評価されるだけでなく、ジャガードをはじめ多種多様な生地を生産している。
商品を見る
栃尾・
見附産地
新潟県
地域ごとに分業制で生産されることが多いなか、新潟県長岡市の栃尾地域は糸から織物に至る工程が地域内に集約されている、全国でも珍しい産地。
化合繊の中肉地素材が得意。また、見附地域は江戸時代から全国有数の織物産地であったが、戦後はニット業も拡大していき、ニットの一大産地にまで成長した。
商品を見る
北陸産地
石川県 福井県 富山県
古くは絹織物で栄えたが、現在はスポーツ、アウトドアなどに多く使われる高密度織物を中心とした合繊の一大産地。
長繊維(フィラメント)の合繊織物・編物(ニット)においては全国の90%が北陸産地で生産され、衣料用だけでなく、産業資材でも多く活用されている。
商品を見る
富士吉田
産地
山梨県
甲斐絹(かいき)を代表とする絹織物の生産を担ってきたことから、先染め・細番手・高密度を特徴とする絹織物が有名。
富士山の雪解け水は染色に適しており、発色が際立つことも特徴の一つである。
第二次世界大戦以降は、絹だけでなく合成繊維やキュプラでの製造も開始され裏地、ネクタイ生地、インテリア生地など幅広く使用されている。
商品を見る
遠州産地
静岡県
静岡県西部の遠州産地は、三河(愛知)、泉州(大阪)と並ぶ、日本三大綿織物産地として知られている。
ポプリン、金巾(かなきん)、朱子(しゅす)などの後染め綿織物をメインとしているが、太番手織物から細番手まで幅広い素材が生産可能。
シャトル織機の保有数が多いことも特徴の一つで、伝統的な温かみのあるからみ織の技術が残っている。
商品を見る
天龍社
産地
静岡県
日本で唯一の別珍・コーデュロイの産地で、国内シェアの95%を占めている。
帆布や雲斎織などの厚地の綿織物を取り扱うノウハウが蓄積されていったことが、コーデュロイが製造される礎になっていった。
現在はファッションのみならずインテリアや資材にまで多様化を見せているが、高齢化が深刻化し、未来の担い手を必要としている。
商品を見る
三河産地
愛知県
「三河木綿」「知多晒」などの綿織物の白生地産地。日本三大綿織物産地として名を馳せ、衣料用に限らず日用品や資材など幅広い分野の織物を生産している。
知多では甚平・手ぬぐい・ガーゼなどの用途で0.5mほどの小巾織物が生産され、蒲郡では産業・寝装・インテリア用織物やファンシークロスなど柄物が生産されている。
商品を見る
尾州産地
愛知県 岐阜県
全国シェアの70%以上を占めている国内最大の毛織物の産地。イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールド、愛知県の西部~岐阜の一部にある尾州が毛織物の世界三大産地と呼ばれている。
紳士用スーツ地、コートなどの高級ゾーンに多く用いられており、最大の特徴としては、糸から織物を作るまでの全工程がこの地域でなされ、分業体制が整っていること。
産地内で完結することにより、多品種・少量・短サイクルの生産が可能。
尾州産地の詳しい話はこちら
商品を見る
湖東産地
滋賀県
日本最古の麻織物の産地として知られている。
「近江上布(おうみじょうふ)」など高級麻織物が有名。
鈴鹿山系から流れてくる豊富な地下水や、琵琶湖から発する湿気が多い土地柄を活かし、麻織物産地として発展した。
商品を見る
京都産地
京都府
日本最大の和装絹織物の産地です。国内の和装(着物等)白生地の約60%を生産している。
独特の凹凸感(シボ)をもつ「丹後ちりめん」が有名で、伝統工芸も多く、金襴織、絞り染め、墨流し、かご染めなども特徴の一つ。
シルクの染に関してはどの産地よりも優れており、プリント技術も手捺染からインクジェットまで可能な産地。
商品を見る
泉州産地
大阪府
1500年初頭に三河発祥の綿織と技術は和泉国に普及され、泉州の気候や土壌が絹の栽培に適しており、「和泉木綿(いずみもめん)」をきっかけに綿織物の産地として有名となった。
白生地綿織物をメインに取り扱い、衣服だけでなく、寝装、シーツ、産業資材、浴衣、衛生材料ガーゼ等、多品種の製織を行っている。
商品を見る
播州産地
兵庫県
先染めした糸で柄を織る「播州織」が有名。糸を先に染めてから織物にしているため、ナチュラルな風合いと素晴らしい肌触りをもつ生地に仕上がる。
シャツ地をメインに、ハンカチ、テーブルクロスなど様々な製品に加工されており、播州産地で作られる先染め織物は国内生産の約70%のシェアを占めている。
商品を見る
高野口
産地
和歌山県
パイル織物に特化した産地。古くは江戸時代の木綿織物にはじまり、明治初期にパイル織物にルーツである「再織」と呼ばれる技法が創案された。
パイル織・編物とは、生地の基布にパイル糸が編込まれている特殊な有毛生地の事で、服地やエコファー(フェイクファー)の他、カーシート、寝装寝具、インテリア、おもちゃなど、幅広い分野で使用されている。
商品を見る
今治産地
愛媛県
明治以前は綿の白生地やネル生地を多く織っていたが、明治27年よりタオルの製織を開始。
現在は「今治タオル」で有名な日本最大のタオルの産地となっており、国産タオルの60%弱の全国シェアを有している。
商品を見る
三備産地
岡山県 広島県
岡山県倉敷市児島の「備前地区」、岡山県井原市の「備中地区」、広島県福山市の「備後地区」によって形成されている。
それぞれ学生服・デニム素材・ワーキングウェアの産地として有名。産地内はジーンズメーカーのほか洗い加工、ダメージ加工などの関連事業者が集積する。
また、特殊刺繍、プリーツ加工、金襴緞子などの工場があるのも特徴的。
商品を見る
博多・
久留米
産地
福岡県
福岡県博多地域は、帯などに使われる厚地の絹織物の「博多織」の産地。
また、久留米地域は江戸時代から伝わる伝統的な久留米絣で知られる産地である。
今でこそ高級品ではあるが、当時は庶民の日常着として流通していたとされる。
昭和に入ってからは半纏の製造が盛んになり、現在は綿入り半纏の国内シェア90%以上を誇る。
商品を見る